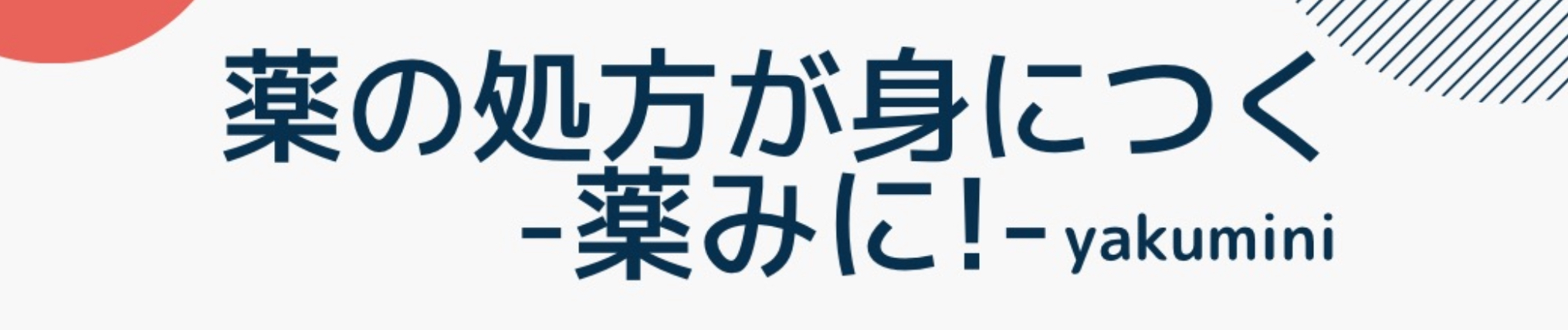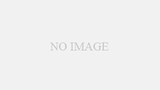高齢になると不眠を訴える方が増えますね。
若い時と同じように眠れないことは仕方のないことですが
実際どのように睡眠の評価とアドバイスをしたらよいでしょうか。
また、すでに眠剤を大量に飲んでる状態から診ることも多いですね。
そんな時の眠剤減量の1つの案としてベンザリンの使い方も参考にしてください。
睡眠衛生指導
睡眠効率
- 目標:85%以上
- 睡眠効率=眠った時間÷横になってた時間
横になっていた時間に対して実際に眠っていた時間の割合。
- 不眠症では寝付くまで長く、中途覚醒もあるため睡眠効率は60%を切ることが多い。
例
- 0時:睡眠薬を服用、横になる
- 2時:寝つく
- 4時:目が覚める
- 7時:まで眠れなかった
寝てる時間が2時間÷横になっていた7時間=29%(睡眠効率)となる。
- 眠くなってから睡眠薬を服用し、布団に入るようにする。
眠くなってからベッドに入る
- 眠くないのにベッドにいると、ベッドに入ると眠れるという条件反射が失われる。
- 目が覚めて眠れないようならベッドから一旦離れる。
- 一時的に睡眠時間が減る可能性があるが、睡眠効率を上げる方が改善につながる。
高齢者の不眠
- 「昼間も眠くないから昼寝もできない」
→睡眠が足りている。 - 「夜眠れないから昼寝している」
→昼寝が原因で夜眠れない。
睡眠効率=入床時間と起床時間(ベッドにいる時間)を確認する
入眠時間と覚醒時間より重要
- 高齢者の睡眠時間は生理的に6hとされる。
- 夜9時にベッドに入り、朝6時に起きようとしていると、生理的な入眠時間と3hも差がある。
→寝付けなかったり、途中で起きたり、不眠の訴えにつながる。 - 「赤ちゃんは1日のほとんど寝ている。大きくなるに連れて睡眠時間が減り、大人になると仕事をするために睡眠時間を削る。高齢者になって必要な睡眠時間は増える訳ではない。」
鑑別を考えよう
レストレスレッグス
- 自発的に語られないため、こちらから聴取する。
- 特に高齢者・女性・妊婦・腎機能障害に多い。
- 治療薬はニュープロパッチやビ・シフロールなどのパーキンソン病治療薬。
睡眠相後退症候群
- 睡眠のリズムがどんどん遅くなり、夜に寝付けず、朝になって眠くなる。
- 夜更かし、朝に起きないことが原因となる。
- 眠れる時間がずれてるだけで、生理的には眠れるため睡眠薬が効かない。
- 生活指導が大事。必ず朝に起きること。
- 使うなら睡眠のリズムを治すラメルテオン(ロゼレム)が効くかもしれない。
睡眠薬依存
- 睡眠薬を服用しないと眠れなくなる。
- 特に短時間作用型の睡眠薬で依存が強い。
Z系(ゾルピデム(マイスリー)、ゾピクロン(アモバン)、エスゾピクロン(ルネスタ))はBZDの中で依存は弱い方だがそれでも依存しうる。
- 対応としては間隔を減らすか、量を減らして調整していく。
ニトラゼパム(ベンザリン)
患者が睡眠薬を減らす気がない場合はニトラゼパム(ベンザリン)に変えてみる。
- ニトラゼパム(ベンザリン)は中時間型作用であり依存が少ない。
- 10mg錠、5mg錠、2mg錠がある。
- 10mgから9→8→7mgと細かく減量できるため抵抗なく実践しやすい。
「高齢になると薬も強く効きやすくなってくるので、適正量にするために薬を少し変更してみましょう〜。」